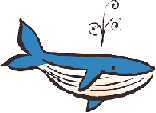 |
八戸化石クジラ
|
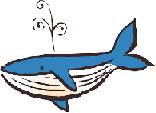 |
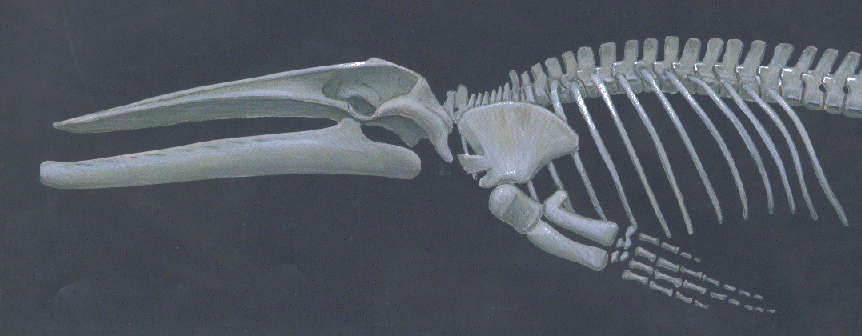 クジラは地質時代の新生代(6千5百万年前〜現在)に、この地球上に現れた世界最大のホ乳動物です。それまでの地球は、恐竜(大型のハ虫類)の世界で、ホ乳類はネズミのような小さな体でひっそりと生活していました。6千5百万年前、恐竜が絶滅すると、ほ乳類は生活の場を広げていきました。海にその場を求めたのがクジラの仲間です。初期のクジラは歩行のための足をもっていましたが、進化の過程で、現在のクジラは後ろ足が退化しています。しかし、前足(前のヒレ)には指の骨が残っています。
クジラは地質時代の新生代(6千5百万年前〜現在)に、この地球上に現れた世界最大のホ乳動物です。それまでの地球は、恐竜(大型のハ虫類)の世界で、ホ乳類はネズミのような小さな体でひっそりと生活していました。6千5百万年前、恐竜が絶滅すると、ほ乳類は生活の場を広げていきました。海にその場を求めたのがクジラの仲間です。初期のクジラは歩行のための足をもっていましたが、進化の過程で、現在のクジラは後ろ足が退化しています。しかし、前足(前のヒレ)には指の骨が残っています。
今回の八戸化石クジラは、新生代第三紀鮮新世(510万〜170万年前)の地層(斗川層)から見つかりました。平成5年にも、尻内町蛇の沢の地層から化石クジラ(下顎の骨と腰椎骨)が発見され、この時の発掘調査で、地層中の火山灰(HATF1)が、放射性元素による年代測定で360万±50万年前のものと分かっています。この火山灰層のすぐ下の層から今回の化石クジラは出てきました。このことから、クジラは360万年前に生きていたことが推定されます。
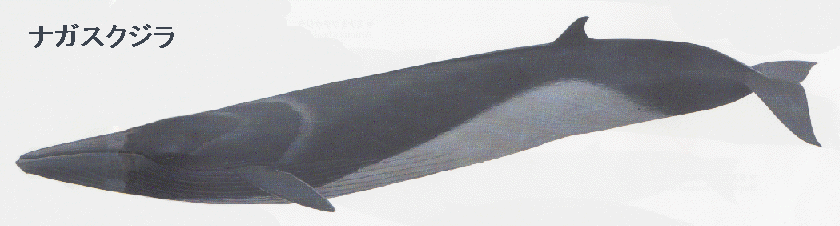 360万年前は、人類の祖先アウストラロピテクスがアフリカの大地に生活しはじめたころで、現在のヒトよりもオランウータンに近いものだったと考えられています。しかし、クジラの仲間は6千5百万年前に地球上に現れ、長い間に進化をしてきたため、この頃のクジラと現在のクジラには大きな違いはないようです。八戸化石クジラは骨格の特徴やその大きさから、ヒゲクジラ類のナガスクジラの仲間と考えられます。
360万年前は、人類の祖先アウストラロピテクスがアフリカの大地に生活しはじめたころで、現在のヒトよりもオランウータンに近いものだったと考えられています。しかし、クジラの仲間は6千5百万年前に地球上に現れ、長い間に進化をしてきたため、この頃のクジラと現在のクジラには大きな違いはないようです。八戸化石クジラは骨格の特徴やその大きさから、ヒゲクジラ類のナガスクジラの仲間と考えられます。
当時の八戸市周辺は、階上岳を除いてほとんどが海底でした。このことはクジラ化石のまわりからたくさんの貝の化石が出てくることからも分かります。
また、現在のクジラは、ハワイなどの暖かい海にも、また南氷洋のような冷たい海でも生活しています。このため、クジラの化石が出てきても、当時の八戸周辺はどのような海だったかは推定できません。しかし、まわりから出てくる貝化石を調べることによって、当時の環境を考えることができます。現在、この貝化石の調査も進めています。
 化石クジラの発見は、青森県内では八戸のものを除いて4件の報告がありますが、平成4年に岩木町中村川で発見され、青森県立郷土館が発掘したものを除けば、骨片程度で種類の確定はおろかクジラであることもはっきりしない資料だけです。尻内町の地層からは、今回のものの他に、6件のクジラの化石が見つかっています。尻内町付近の丘陵は「クジラの丘」といってもいいほどの貴重な地域です。
化石クジラの発見は、青森県内では八戸のものを除いて4件の報告がありますが、平成4年に岩木町中村川で発見され、青森県立郷土館が発掘したものを除けば、骨片程度で種類の確定はおろかクジラであることもはっきりしない資料だけです。尻内町の地層からは、今回のものの他に、6件のクジラの化石が見つかっています。尻内町付近の丘陵は「クジラの丘」といってもいいほどの貴重な地域です。
今回のクジラ化石は、残念ながら、頭から腰にかけての4分の3の部分は、砂取り作業で削り取られたためか、残っていません。また、尾椎の先端の小さな骨や尾椎の下にあるV字骨は、地層の中で溶けてしまったようで、残っていませんでした。しかし、これまでの化石と違い、17個の椎骨がつながった状態で出てきました。このことは、波や海の流れの影響を受けず、骨がバラバラになる前に土砂に埋もれたことを示しています。
 これまで貝化石は出てくるものの、保存状態が悪く標本採集は難しいものばかりで、ほとんど調査されていない八戸地方の新第三紀の地質でしたが、この化石クジラの発掘によって、地層の堆積当時の環境(古環境)や、地球の歴史(地史)を考えていく上でもたいへん貴重で、詳細に分かれば学術的にも重要なものと考えます。それにもまして、八戸の子供たちにとって化石クジラは、八戸の過去を想像できる最大の宝物であり、後世に残すべき貴重な資料だと思います。
これまで貝化石は出てくるものの、保存状態が悪く標本採集は難しいものばかりで、ほとんど調査されていない八戸地方の新第三紀の地質でしたが、この化石クジラの発掘によって、地層の堆積当時の環境(古環境)や、地球の歴史(地史)を考えていく上でもたいへん貴重で、詳細に分かれば学術的にも重要なものと考えます。それにもまして、八戸の子供たちにとって化石クジラは、八戸の過去を想像できる最大の宝物であり、後世に残すべき貴重な資料だと思います。
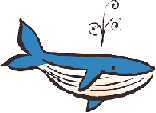
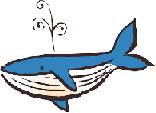
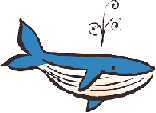
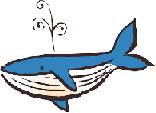
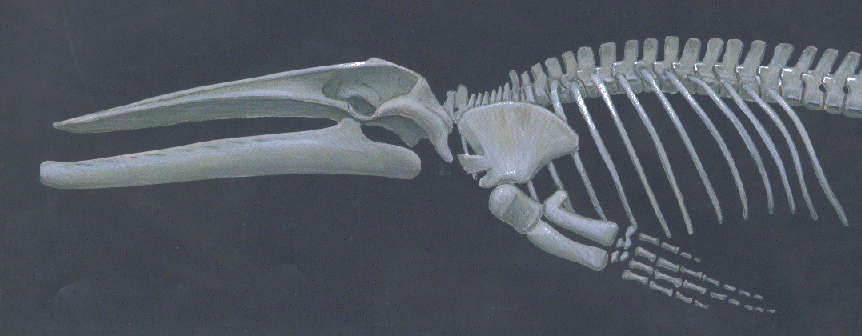 クジラは地質時代の新生代(6千5百万年前〜現在)に、この地球上に現れた世界最大のホ乳動物です。それまでの地球は、恐竜(大型のハ虫類)の世界で、ホ乳類はネズミのような小さな体でひっそりと生活していました。6千5百万年前、恐竜が絶滅すると、ほ乳類は生活の場を広げていきました。海にその場を求めたのがクジラの仲間です。初期のクジラは歩行のための足をもっていましたが、進化の過程で、現在のクジラは後ろ足が退化しています。しかし、前足(前のヒレ)には指の骨が残っています。
クジラは地質時代の新生代(6千5百万年前〜現在)に、この地球上に現れた世界最大のホ乳動物です。それまでの地球は、恐竜(大型のハ虫類)の世界で、ホ乳類はネズミのような小さな体でひっそりと生活していました。6千5百万年前、恐竜が絶滅すると、ほ乳類は生活の場を広げていきました。海にその場を求めたのがクジラの仲間です。初期のクジラは歩行のための足をもっていましたが、進化の過程で、現在のクジラは後ろ足が退化しています。しかし、前足(前のヒレ)には指の骨が残っています。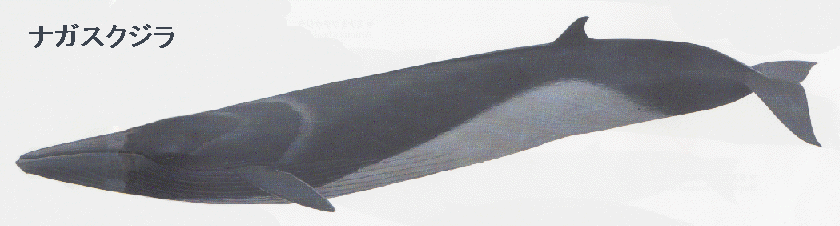 360万年前は、人類の祖先アウストラロピテクスがアフリカの大地に生活しはじめたころで、現在のヒトよりもオランウータンに近いものだったと考えられています。しかし、クジラの仲間は6千5百万年前に地球上に現れ、長い間に進化をしてきたため、この頃のクジラと現在のクジラには大きな違いはないようです。八戸化石クジラは骨格の特徴やその大きさから、ヒゲクジラ類のナガスクジラの仲間と考えられます。
360万年前は、人類の祖先アウストラロピテクスがアフリカの大地に生活しはじめたころで、現在のヒトよりもオランウータンに近いものだったと考えられています。しかし、クジラの仲間は6千5百万年前に地球上に現れ、長い間に進化をしてきたため、この頃のクジラと現在のクジラには大きな違いはないようです。八戸化石クジラは骨格の特徴やその大きさから、ヒゲクジラ類のナガスクジラの仲間と考えられます。 化石クジラの発見は、青森県内では八戸のものを除いて4件の報告がありますが、平成4年に岩木町中村川で発見され、青森県立郷土館が発掘したものを除けば、骨片程度で種類の確定はおろかクジラであることもはっきりしない資料だけです。尻内町の地層からは、今回のものの他に、6件のクジラの化石が見つかっています。尻内町付近の丘陵は「クジラの丘」といってもいいほどの貴重な地域です。
化石クジラの発見は、青森県内では八戸のものを除いて4件の報告がありますが、平成4年に岩木町中村川で発見され、青森県立郷土館が発掘したものを除けば、骨片程度で種類の確定はおろかクジラであることもはっきりしない資料だけです。尻内町の地層からは、今回のものの他に、6件のクジラの化石が見つかっています。尻内町付近の丘陵は「クジラの丘」といってもいいほどの貴重な地域です。 これまで貝化石は出てくるものの、保存状態が悪く標本採集は難しいものばかりで、ほとんど調査されていない八戸地方の新第三紀の地質でしたが、この化石クジラの発掘によって、地層の堆積当時の環境(古環境)や、地球の歴史(地史)を考えていく上でもたいへん貴重で、詳細に分かれば学術的にも重要なものと考えます。それにもまして、八戸の子供たちにとって化石クジラは、八戸の過去を想像できる最大の宝物であり、後世に残すべき貴重な資料だと思います。
これまで貝化石は出てくるものの、保存状態が悪く標本採集は難しいものばかりで、ほとんど調査されていない八戸地方の新第三紀の地質でしたが、この化石クジラの発掘によって、地層の堆積当時の環境(古環境)や、地球の歴史(地史)を考えていく上でもたいへん貴重で、詳細に分かれば学術的にも重要なものと考えます。それにもまして、八戸の子供たちにとって化石クジラは、八戸の過去を想像できる最大の宝物であり、後世に残すべき貴重な資料だと思います。