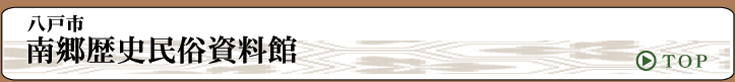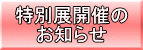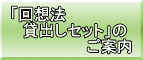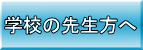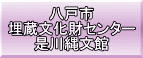八戸市南郷歴史民俗資料館の隣にはダムに沈んだ世増地区から移築した民家があります。
八戸市南郷歴史民俗資料館の隣にはダムに沈んだ世増地区から移築した民家があります。明治の中頃に建築された建物で、5間×8間の一般的な大きさです。
間取りは、にわ(土間)、厩(うまや)、ちゃま(居間)、じょうや(物置)、寝部屋、でい(奥座敷)、こざ(奥座敷)となっています。
台所が無いのが特徴で、囲炉裏で調理や煮炊きをしていました。
八戸市南郷歴史民俗資料館をご見学されると、古民家の内部もご覧になることができます。
■昔の人びとの暮らし■
 |
 |
 |
| 囲炉裏。食べ物の煮炊きをするので、一年中火が焚かれていました。 | 麻から糸をとり、機(はた)で織って衣類を作っていました。 | 豆腐作りの道具。大豆から作る豆腐はごちそうでした。特別な日には、家で作りました。 |
 |
 |
 |
| 味噌玉。味噌は、重要なたんぱく源でした。大豆を煮て、つぶして、味噌玉にして発酵させて、味噌を作りました。 | わら布団。布団の中には、わらを使いました。 | えんつこ。わらを編んだもので、赤ちゃんを入れておきました。現在のベビーベッドです。 |