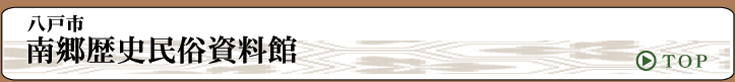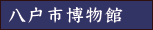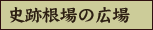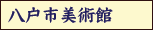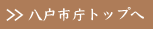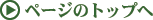世増(よまさり)ダム模型
平成16年に、八戸市世増地区に地域の人々が安全で安心して生活を営めるようにという願いを込めたダムが完成しました。・世増ダムの役目
・世増ダム建設の経緯 → 「南郷地区について」
・世増地区の模型

学 校
江戸時代には、武士は幕府直営の学校や諸藩が運営する藩校、庶民は寺子屋、郷学、塾などで学びました。明治5年に学制が発布され、下等小学校4年、上等小学校4年となりました。
明治19年には尋常小学校4年、高等小学校4年となり、尋常小学校は義務教育となりました。
そして、明治40年に尋常小学校6年、高等小学校2年となり、終戦まで続きました。
戦後、昭和22年に学校教育法が公布され、現在の小学校6年、中学校3年が義務教育となりました。

南郷区の学校
南郷区の学校は、様々な名前や形を変え、多くの学生を育ててきました。小学校・中学校の変遷 → 「南郷地区について」
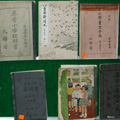
教科書制度の変遷
政府は、明治5年、学制公布後、師範学校を設け、小学校教師のための近代的な教育方法の伝習にあたりました。当時、まだ教科書の編纂事業が充分進んでおらず、小学校用の教科書は民間で出版された翻訳書や啓蒙書が大半を占めていました。
これらは生徒にとって難解な内容であったため、教育現場からは生徒の学力に応じた学年別の教科書の編纂が望まれました。
そこで文部省は「小学入門」「小学読本」「小学算術」など、欧米の教科書を参考に新しい教科書の編纂を行いました。
明治19年小学校令の公布により小学校の教科書は文部大臣が「検定シタルモノニ限ルベシ」と定め、教科書の検定制度が始まりました。
明治36年小学校令の改正により、小学校の教科書は「文部省ニ於テ著作権ヲ有スルモノタルベシ」と定められ教科書の国定制度がスタートしました。

明かり
人類が炎を手にした時から、明かりの歴史が始まりました。たき火、ろうそく、あんどん、ランプと、明かりは長い間「炎」が用いられ、暮らしを照らしてきました。
そして、エジソンが1879年(明治12)に実用的な白熱電球を発明したことにより、電気の光となって行きます。
日本では1887年(明治20)に東京電力が設立され、徐々に明るい光の中での暮らしが出来るようなりました。

電 話
1876年(明治9)、アメリカでグラハム・ベルが電話を発明しました。日本での電話操業は、1890年(明治23)東京・横浜間で始まりました。
八戸では、1908年(明治41)年に開通しました。
電話機はダイヤル式でしたが、1969年(昭和44)にプッシュ式が開発され、現在はすべてこの方式になっています。

計算機
日本では、中世のころ中国から伝わった算木、算盤(そろばん)などが使われていました。手動式機械歯車式の計算機は大正12年ころに登場し、昭和30年代まで利用されました。
昭和38年、電子式卓上計算機が開発され、以降飛躍的な発展をとげ身近な物になりました。

蓄音機・レコード
1877年(明治10)、エジソンが錫(すず)を塗った円筒に録音して、再生することができる蓄音機を発明しました。その後、電話機の発明で有名なベルが改良型蓄音機として、厚紙にロウをぬった円筒に録音して、サファイア針で再生する蓄音機を開発しました。
そして、ベルの蓄音機開発チームで働いていたベルリナーが、1887年(明治20)円盤に音を刻み込む方式の蓄音機を開発しました。この円盤は大量にプレスすることができ、レコードの発明となりました。
日本では、1889年(明治22)鹿鳴館で初公開されました。