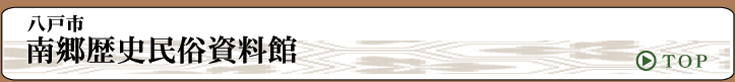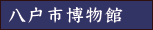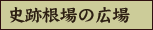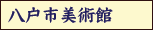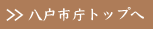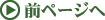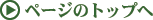ラジオ
1922年(大正11)、アメリカでラジオ放送が始まりました。日本では、1925年(大正14)3月22日、ラジオ放送が開始されました。
この日、午前9時30分の「JOAK・JOAK、こちらは東京放送局であります」が第1声。この後、読売新聞ニュースやソプラノ独唱が続き、終わりが20時55分の天気予報だったそうです。
昭和30年代にテレビが普及するまでは、情報源や娯楽の主役でした。

テレビ
1935年(昭和10)、ドイツで世界初の試験放送が開始されました。日本では、1953年(昭和28)2月1日午後2時、NHKテレビの本放送が始まりました。
開局の第1声は「JOAK−TV こちらはNHK東京テレビジョンであります」でした。
開局式の後、尾上松緑らによる舞台劇「道行初音旅」がオンエアされ、これが日本初のテレビ番組となりました。当時の受信契約数は866件でした。
当時アメリカ製の17インチテレビが25万円。サラリーマンの手取り月収が1万5千円でしたので、とても家庭では持つことはできませんでした。
その後、昭和30年代になり、力道山ブーム、美智子妃ブームを経て、一気に普及して行きました。

洗 濯
洗濯板を使っての手洗いでしたが、手回しの洗濯機が登場し、昭和30年代からは電気洗濯機が普及しました。初期の電気洗濯機は、ローラー式の脱水装置でした。

カメラ・写真の歴史
1826年、フランスでニエプス兄弟がアスファルトを感光版に風景を撮影し、初めて画像を固定することに成功しました。しかし、撮影には8時間もかかりました。1841年、イギリスのタルボットが焼増しの出来るネガ・ポジ法を開発しました。撮影時間は3分ほどになりました。
その後、湿板写真法、乾板写真法、銀板写真と開発され、銀板写真では生産された製品を用いて撮影できるため写真の普及につながりました。
現在のようなロール型のフィルムは、1888年(明治21)にアメリカのイーストマン社が開発しました。
日本へは、1841年(天保12)にオランダから伝えられ、島津藩主を撮影した銀盤写真が初の写真となり、現存しています。

おもちゃ
ブリキ製のおもちゃ、ボードゲームなどなつかしい玩具がたくさんあります。
たばこ
1200年代末、コロンブスが米大陸と葉たばこを発見しました。日本には、1543年種子島に鉄砲とともに伝わったと言われています。
江戸時代までは刻みたばこで、煙管(きせる)で吸っていました。明治になって、外国から紙巻たばこが入ってきました。
■南郷区の葉たばこ栽培
南郷区は、葉たばこの栽培が盛んな地区です。葉たばこは、栽培・乾燥に手間や技術を要しますが、買い取り制で価格が安定していることなどから栽培が盛んになりました。
昭和13年 農業試験場五戸分場で10アール試作
昭和15年 中沢、島守両村で本格的栽培始まる
昭和34年 島守地区に取扱所建設記念碑とたばこ神社を建立する
昭和39年 中沢支部の売上代金1億円突破
昭和40年 島守支部の売上代金1億円突破
平成 6 年 南郷村の売上代金17億6,400万円 (史上最高)
現在は、健康への影響からたばこを吸う人が減っており、生産量500トン、販売額10億円ぐらいになっています。

消防の歴史
消防団は、江戸時代の火消組「いろは四八組」に始まります。火消組はお互いの名誉にかけて競い合って消火活動にあたったため、消防の発展につながりました。江戸時代は、竜吐水(りゅうどすい)という消火ポンプがありましたが、水量が少なかったため、あまり役に立ちませんでした。そこで、建物などの燃える物を壊して、燃え移らないようにするという消火法でした。
明治になると、知事が消防事務を管掌する制度ができましたが、全国統一化された組織体制ではありませんでした。このころの現場指揮はすべて警察が行っていました。
明治13年に、東京府で消防を東京警視庁から分離し、内務省直轄の消防本部(現東京消防庁の前身)を設立しました。これが、現在の消防制度の始まりとなりました。
消化ポンプも、大型の物や蒸気式のポンプが導入され、消火能力が増しました。
■南郷区の消防組織 → 「南郷地区について」

戦時中のくらし
昭和の前期は、戦争の時代でした。戦う兵隊はもちろんですが、家を守る人々も厳しい生活を送りました。衣類・食糧は国からの配給制となり、学校でも軍事訓練や食糧の生産を行いました。「ぜいたくは敵だ」を合言葉にぎりぎりの生活が続き、空襲におびえながらくらしていました。